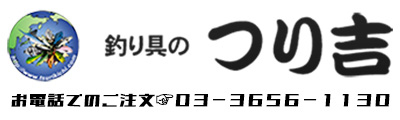湾奥シーバス釣りに必要な道具
ルアーフィッシングの場合
ルアーフィッシングは、ルアーをキャストして広範囲を探り、シーバスの活性や捕食パターンに合わせて様々なルアーを使い分ける、能動的な釣り方です。
1. 竿 (ロッド)
都内のシーバス釣りでは、狭い運河やストラクチャー(障害物)周りを狙うことが多いため、取り回しの良い長さが好まれます。
シーバス専用ロッド:
長さ: 6フィート6インチ(約1.98m)〜9フィート(約2.74m)前後が主流です。
短い竿(6.6ft〜7.6ft): 運河やバース(岸壁)打ち、橋脚などのピンスポットを狙うのに適しています。キャスト精度が求められる場面で有利です。
長い竿(8ft〜9ft): 河川やオープンエリアで遠投したい場合や、足場の高い場所で有利です。
硬さ(アクション): ML(ミディアムライト)〜M(ミディアム)クラスが一般的です。
MLクラス: 軽量ルアーの操作性やシーバスの繊細なアタリを取りやすい。
Mクラス: 重めのルアー(20g〜30g超)を快適にキャストでき、大型シーバスとのファイトにも対応しやすい。
例: シマノ「ルナミス」「ディアルーナ」、ダイワ「ラテオR」「モアザン」など。
2. リール
ルアーを素早く回収したり、シーバスの瞬発的な引きに対応するため、スムーズな巻き心地とドラグ性能が重要です。
スピニングリール:
番手: シマノならC3000番〜4000番、ダイワならLT3000番〜LT4000番クラスが適しています。PEライン1号〜1.5号が150m〜200m巻けるラインキャパシティがあると安心です。
ギア比: ハイギア(HG)またはエクストラハイギア(XG)モデルがおすすめです。素早いルアー回収や、シーバスの突進に対応しやすいです。
例: シマノ「ストラディック」「ツインパワー」、ダイワ「ルビアス」「セルテート」など。
3. 道糸 (メインライン)
飛距離と感度、強度を兼ね備えたラインが必須です。
PEライン:
太さ: 0.8号〜1.5号が一般的です。飛距離を重視するなら細め、ストラクチャー周りをタイトに攻めるなら太めを選ぶこともあります。
長さ: 150m〜200mあれば十分です。
注意点: 4本撚りより8本撚り(8ブレイド)の方が、強度と滑らかさに優れ、飛距離も出やすい傾向があります。
4. リーダー
PEラインの保護と、シーバスの鋭いエラ洗いによるラインブレイクを防ぐために必須です。
フロロカーボンリーダー:
太さ: 16lb(約4号)〜30lb(約8号)程度。シーバスのサイズや、狙うポイント(障害物の有無)によって使い分けます。
長さ: 1m〜2m程度。長すぎるとキャスト時にガイドに絡みやすくなるため、適切な長さに調整しましょう。
結び方: PEラインとの結束は、強度のあるFGノットやPRノットなどでしっかり行いましょう。
5. ルアー
シーバスルアーは種類が非常に豊富です。狙うレンジ(水深)や状況に合わせて使い分けます。
ミノー: 表層〜中層を広く探れる定番ルアー。リップの有無や形状で潜行深度が変わります。
フローティング、シンキング、サスペンド: それぞれ水に浮く、沈む、浮きも沈みもしない特性があり、状況で使い分けます。
サイズ: 90mm〜140mm程度。
例: シマノ「エクスセンス サイレントアサシン」、ダイワ「ショアラインシャイナー」など。
バイブレーション: 飛距離が出やすく、広範囲を探ったり、強い波動でアピールしたりするのに適しています。中層〜底層を効率的に探れます。
サイズ: 70mm〜90mm程度。
例: バスデイ「レンジバイブ」、コアマン「VJ-22 / VJ-28」など。
シンキングペンシル: 水平姿勢で沈み、ナチュラルな動きで食わせるタイプ。ナブラ撃ちや、食い渋るシーバスに有効です。
サイズ: 80mm〜120mm程度。
ワーム(ジグヘッドリグ): ソフトな動きと食い込みの良さが特徴。特にナイトゲームや食い渋る状況で有効です。
エサ釣り(ぶっこみ釣り・ウキ釣りなど)の場合
エサ釣りは、生きたエサや切り身を使ってシーバスを狙う方法です。手軽に始められ、ルアーに反応しないシーバスにも有効な場合があります。
1. 竿 (ロッド)
ルアーロッドよりもやや長めで、エサを投入しやすく、魚の引きを受け止めやすいものが良いでしょう。
磯竿、投げ竿、または汎用的なルアーロッド(M〜MHクラス):
長さ: 3m〜5m程度。足元から少し沖に仕掛けを投入し、魚の引きをいなすのに適しています。
硬さ: 2号〜4号程度の磯竿や、ライトな投げ竿(20号〜25号負荷程度)が扱いやすいでしょう。
例: 汎用的な磯竿、安価な投げ竿セットなど。
2. リール
スピニングリール:
番手: 3000番〜4000番クラス。道糸を200m程度巻けるもの。
特徴: 安価なものでも十分に楽しめます。
3. 道糸 (メインライン)
ナイロンライン:
太さ: 3号〜5号が一般的です。根ズレや大物がかかった際の強度を考慮します。
長さ: 150m〜200mあれば十分です。
PEライン: 感度を重視する場合はPEラインも使えますが、その際はリーダーは必須です。
4. リーダー
フロロカーボンリーダー: ナイロンラインを使用する場合は不要なこともありますが、PEラインを使用する場合は必須です。
太さ: 20lb〜40lb(約5号〜10号)。
長さ: 1m〜2m。
5. オモリ
ナス型オモリ、六角オモリなど:
号数: 5号〜20号程度。潮の流れやポイントの深さ、使用する竿に合わせて調整します。遊動式の仕掛けで使うことが多いため、中通しオモリも有効です。
6. 仕掛け
ぶっこみ釣り仕掛け: オモリを底に沈め、エサを底付近に置くシンプルな仕掛け。
遊動式天秤仕掛け: オモリの上に天秤を介してハリスを接続するタイプ。アタリが取りやすく、絡みにくい。
胴突(ドウヅキ)仕掛け: 幹糸に複数の枝針を出すタイプ。
ハリス: フロロカーボンラインの3号〜6号を50cm〜1m程度。
針: シーバス針、セイゴ針、チヌ針など、エサのサイズに合わせて選びます。
ウキ釣り仕掛け: ウキを付けて、エサを中層に漂わせる釣り方。
棒ウキ、電気ウキ: 夜釣りでは電気ウキが必須です。
シモリ玉、ウキ止めゴム: タナを調整するための小物。
7. エサ
イワシ(活きエサまたは切り身): シーバスの好物で、定番のエサです。活きエサは釣具店で購入できます。
アジ(活きエサまたは切り身): イワシと同様に有効です。
サッパ、コノシロなど: 他の小魚も使われます。
アオイソメ、ゴカイ: 虫エサも使われることがありますが、小魚系のエサの方が大型シーバスには効果的です。
その他のあると便利な道具(共通)
プライヤー: 針外しやラインカットに。
ハサミ: エサカット用。
フィッシュグリップ: シーバスの鋭いエラから手を守り、安全に魚を掴むために必須です。
ランディングネット (タモ): 足場が高い場所や大型のシーバスを取り込む際に必須です。柄の長いもの(5m〜6m程度)が都内では役立ちます。
クーラーボックス: 釣れたシーバスを持ち帰る場合。
タオル: 手拭き用。
ライフジャケット: 安全のため必ず着用しましょう(特に水辺に近接する釣り場では必須です)。
ヘッドライト: 夜釣りでは必須です。
偏光グラス: 水面のギラつきを抑え、水中やルアーの動き、魚の視認性を高めます。
キャップ/帽子: 日差し対策。
都内23区内のシーバス釣りスポット例
隅田川、旧中川、荒川、多摩川などの河川敷
豊洲ぐるり公園、晴海埠頭などの港湾部
運河沿いの護岸など
注意点: 釣り禁止エリアでないことを事前に確認し、ゴミは必ず持ち帰りましょう。夜間の釣りでは、特に周囲の安全に注意してください。
これらの道具を参考に、ぜひ東京都内でシーバス釣りを楽しんでみてくださいね!