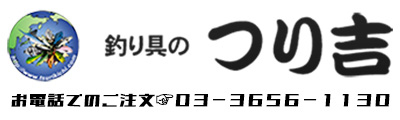都内で手軽に楽しむハゼ釣りに必要な道具
ここでは、ファミリーでハゼ釣りを始めるのにぴったりの、手軽で基本的な道具をご紹介します。
1. 竿 (ロッド)
延べ竿(のべざお): リールがないシンプルな竿で、お子さんでも扱いやすいのが特徴です。
長さ: 2m〜3m程度が、足元や少し先に仕掛けを落とすのに最適です。長すぎると扱いにくく、短すぎるとポイントに届きにくい場合があります。
特徴: 釣具店で「ハゼ釣りセット」として売られているものに含まれていることが多く、非常に安価で手に入ります。
振り出し竿(リール竿): 小型のリールをセットして使う竿です。
長さ: 1.8m〜2.4m程度。少し沖を狙いたい場合や、今後他の釣りにも挑戦したい場合に汎用性があります。
特徴: 小型のスピニングリールとセットで売られている「ちょい投げセット」などが利用できます。
2. リール (リール竿の場合)
小型スピニングリール:
番手: 1000番〜2000番クラス。
特徴: 安価なもので十分です。すでに持っているちょい投げ用のリールがあれば流用できます。
3. 道糸 (メインライン)
ナイロンライン:
太さ: 0.8号〜2号程度。
延べ竿の場合: 竿の先に直接結び付け、竿の長さより少し短めにカットして使用します。
リール竿の場合: リールに巻き付けて使用します。
特徴: 釣具店で巻いてくれる場合もありますし、セットになっているものも多いです。
4. 仕掛け
ハゼ釣りの仕掛けは非常にシンプルです。
市販のハゼ釣り仕掛け: 釣具店で「ハゼ仕掛け」として売られています。これ一つで針、ハリス、ウキ(遊動式)やオモリがセットになっています。
ウキ釣り仕掛け: 水面に浮くウキのアタリでハゼの食い込みを判断します。見ているだけでも楽しいので、ファミリーフィッシングにおすすめです。
ミャク釣り仕掛け(脈釣り仕掛け): ウキを使わず、竿先に伝わるアタリで魚を釣ります。よりダイレクトな引きを感じたい場合に。
スクリュー仕掛け: 近年話題の「ハゼスクリュー仕掛け」は、エサを針に固定するタイプで、エサ持ちが良く、手軽に数を伸ばせるとして人気です。
オモリ: 仕掛けにセットされていることが多いですが、潮の流れや水深に合わせて調整できるよう、予備をいくつか持っていくと良いでしょう。
軽めのナス型オモリやガン玉: 仕掛けをゆっくり沈ませ、ハゼにエサをアピールします。
5. エサ
ハゼは比較的何でも食べる雑食性です。
アオイソメ: 最も一般的なハゼのエサです。釣具店で生きた状態で売られています。
付け方: 短く切って針に刺します。ハゼの口は小さいので、針先を少し出すように小さく付けるのがコツです。
ゴカイ: アオイソメと同様に有効なエサです。
その他: 食料品店で売られているベビーホタテや、近年では虫エサが苦手な方向けに人工エサも販売されています。
6. その他のあると便利な道具
エサ箱: アオイソメなどを入れておくための容器。
ハサミ: アオイソメなどをカットするのに使います。
タオル: 手を拭いたり、汚れた場所を拭いたりするのに使います。
水汲みバケツ: 釣れたハゼを一時的に入れておいたり、手を洗ったりするのに使います。
魚を掴むもの: ハゼはヌルヌルしているので、魚バサミや魚つかみがあると便利です。
クーラーボックス: 釣れたハゼを持ち帰る場合。小型のもので十分です。中に保冷剤や氷を入れておきましょう。
プライヤー/針外し: 針が魚の口の奥にかかった場合に外すのに便利です。
レジャーシートや折りたたみ椅子: 座ってゆっくり釣りたい場合に。
日焼け止め、帽子、飲み物: 快適に釣りを楽しむために。
都内のハゼ釣りスポット例
都内やその近郊には、ハゼが釣れる河川や運河、港湾部が多くあります。
荒川水系(旧中川、新中川など)
隅田川水系(晴海埠頭周辺など)
江戸川水系
多摩川下流域
葛西臨海公園周辺
注意点: 釣り禁止エリアでないことを事前に確認し、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
これらの道具があれば、すぐにでも都内でハゼ釣りを楽しむことができます。お子さんと一緒に、手軽で楽しいファミリーフィッシングを体験してみてくださいね!