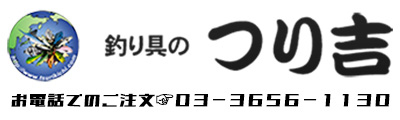アカムツ釣りに必要な道具
波崎・銚子沖のアカムツ釣りは、水深100m〜200m前後の深場を狙う中深場(ちゅうふかば)の釣りです。
アカムツは「赤い宝石」「のどぐろ」とも呼ばれる高級魚で、その繊細なアタリを捉え、口の弱いアカムツをバラさずに釣り上げるための専用タックルが重要になります。
1. 竿 (ロッド)
アカムツのアタリは非常に小さく、また口が切れやすいため、食い込みが良く、バラシにくい調子の竿が求められます。
アカムツ専用竿または中深場用竿:
長さ: 1.9m〜2.3m前後が主流です。手持ちで誘いをかけることが多いため、操作性の良い長さが好まれます。
調子: 6:4〜7:3調子が一般的です。特に、穂先が非常にしなやかで、わずかなアタリも目感度・手感度で捉えられる高感度なものが適しています。船の揺れを吸収し、仕掛けを安定させるクッション性も重要です。
オモリ負荷: 120号〜250号に対応できるもの。波崎・銚子沖では、船宿やポイントによって120号または200号のオモリが指定されることが多いので、事前に確認し、両方に対応できる竿、またはそれぞれのオモリに合った竿を用意すると安心です。
素材: グラスソリッドやUDグラスとカーボンを組み合わせたものが多く、粘り強さと感度を両立しています。
例: シマノ「ディープチェイサー アカムツスペシャル」、ダイワ「極鋭アカムツ」「アナリスターアカムツ」、アルファタックル、アリゲーターなど、各メーカーから専用竿が出ています。
2. リール
深い水深から重い仕掛けと魚を巻き上げるパワーと、手持ちでの操作性を両立できる電動リールが必須です。
番手: PEライン3号〜4号が400m〜500m巻ける、ダイワなら300番〜500番クラス、シマノなら1000番〜3000番クラスが適しています。
水深が比較的浅い(150m前後)波崎のカンネコ根などでは、PE2号〜3号を300m巻ける小型電動リール(ダイワ200番、シマノ600番〜1000番クラス)でも対応可能な場合があります。
銚子沖などより深いポイントや潮が速い場合は、PE4号を400m以上巻ける容量とパワーのあるリールが推奨されます。
特徴: ドラグ性能が高く、巻き上げパワーとスピード調整がしやすいモデルを選びましょう。手持ちでの誘いが多いため、軽量であることも重要です。
例: シマノ「フォースマスター」「ビーストマスター」、ダイワ「シーボーグ」「レオブリッツ」など。
バッテリー: 大容量の電動リール用バッテリー(20Ah以上)は必須です。予備バッテリーもあると安心です。
3. 道糸 (メインライン)
PEライン: 伸びが少なく感度に優れるPEラインを使用します。
太さ: 3号〜4号が一般的です。船宿によっては「PE5号以上の太い道糸は遠慮してほしい」と指定される場合もあるので、事前に確認しましょう。糸の太さがオマツリの原因になることがあります。
長さ: 最低でも400m、できれば500m巻いておきましょう。潮の流れが速い場合や、不意の高切れに備えるためです。
カラーマーキング: 10mごとの色分けや1mごとのマーカーがあるものだと、正確なタナ(水深)の把握に便利です。
4. リーダー
フロロカーボンリーダー: PEラインの先端に接続します。根ズレ対策と、アカムツの口元へのショックを吸収する役割があります。
太さ: 5号〜8号程度。
長さ: 2m〜3m程度。PEラインとの結束は、FGノットなど強度のある結び方でしっかり行いましょう。
5. オモリ
オモリ: 船宿やポイントによって指定される号数が異なります。
波崎沖: 120号または200号が使われます。
銚子沖: 200号を基準に、潮が速い時は250号を使用することもあります。
素材: 多くの船宿で鉛製が指定されます(鉄製や特殊形状のものは使用不可の場合あり)。根掛かりは比較的少ない場所が多いですが、サメなどによる捨て糸切れに備え、予備をいくつか持っていくと良いでしょう。
6. 仕掛け
市販のアカムツ専用仕掛けが便利ですが、自作するアングラーも多いです。
胴突仕掛け: 基本は2本バリです。船宿によっては、資源保護の観点からハリ数を2本までと定めている場合があります。
サバが多い状況では1本バリにする場合もあります。- 天秤吹き流し仕掛け:伊東や宇佐美などの伊豆方面、遠州灘では、天秤吹き流し仕掛けが主流となります。
店主の経験上、胴付きでも成立しますが、基本は天秤の吹き流しになります。
幹糸: 8号〜12号程度。
ハリス: フロロカーボンラインの5号〜8号を50cm〜80cm程度。枝スは消耗品なので、結び替えるための替えバリを10本以上用意しておくと安心です。
捨て糸: 5号〜8号を1m〜1.5m程度。
針: アカムツの口が柔らかくバラしやすい特性を考慮し、ムツ針の16号〜18号、またはホタ針の16号〜17号が定番です。
集魚アイテム: ハリのチモトに**マシュマロボール(浮力体)**を2個付けしてエサの浮遊感をアップさせたり、夜光ビーズやケイムラパイプ、チモトホタルなどを付けたりすることが効果的です。ただし、サメやサバを寄せてしまうこともあるため、状況に応じて脱着できるよう準備しておきましょう。
ヨリトリ器具: 仕掛けの上端には、フジワラ「チビリング」や5連ベアリングサルカンなど、小型のヨリトリ器具を配します。
7. エサ
ホタルイカ: アカムツ釣りの基本エサです。船宿で支給されることが多いですが、追加購入が必要な場合もあります。ワタ付きのゲソ部分を使用するのが一般的です。
サバの切り身: ホタルイカとの抱き合わせで使うと、アピール力が増し、食い込みも良くなることがあります。光沢のある身を使用し、エサ持ちが良いように短冊状にカットします。
抱き合わせ: ホタルイカにサバの切り身を重ねて付けるのが効果的です。
8. その他のあると便利な道具
竿受け (キーパー): 重い竿を安定させるための強力な竿受け。移動中は竿を固定しておくと破損防止になります。
大容量バッテリー: 電動リールを使用する場合、必須です。
プライヤー: 針外しやラインカットに。
ハサミ: エサカット用。
グローブ: 手を保護するため。
タオル: 手拭き用。
クーラーボックス: 釣れたアカムツを鮮度良く持ち帰るためのもの。大型の魚ではないですが、複数匹釣れた場合やゲストフィッシュも考慮し、ある程度の容量があるものが良いでしょう。
神経締めワイヤー・道具: アカムツの鮮度を保ち、美味しく持ち帰るために非常に有効です。
水汲みバケツ: 手を洗ったり、船べりを流したりするのに便利です。
ライフジャケット: 安全のため必ず着用しましょう(多くの船宿で貸し出しがあります)。
カッパ (レインウェア): 波しぶきや雨対策。
酔い止め薬: 船酔いしやすい方は必須です。
マグネット: 仕掛けの針を一時的に固定するのに便利です。
注意点
船宿のルール確認: 最も重要なのは、乗船する船宿のルールと推奨タックルを事前に確認することです。オモリの号数、PEラインの太さ、ハリ数、エサの種類などが細かく指定されている場合があります。
誘いとアワセ: アカムツはアタリが小さく、食い込みに時間がかかることがあります。竿先に出るわずかな変化を見逃さず、焦らず十分に食い込ませてから、ゆっくりと聞き合わせるように竿を立てるのがコツです。
オマツリ対策: 深場での釣りはオマツリ(糸絡み)のリスクが高まります。船長の指示に従い、周囲の釣り人との間隔に注意し、万が一オマツリした場合は速やかに対応しましょう。
安全性: 深場での釣りは危険を伴うことがあります。船長の指示に従い、安全に配慮して釣りを楽しみましょう。
これらの情報を参考に、万全の準備をして波崎・銚子沖のアカムツ釣りに挑戦してみてください!「赤い宝石」との出会いを願っています。